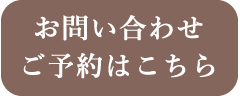低音障害型感音性難聴の治療タイミングはいつがベスト?

こんにちは、冷です。 突発性難聴の治療が早ければ早いほど受けたほうがいいというのは一般常識として知られてますが、低音障害型感音性難聴の治療ベストタイミングはいつかよく聞かれますが。今日このお話をしようと思います。
低音障害型感音性難聴は突発性難聴の一種として扱われることが多く、特に低音域(通常250~500Hz)の聴力低下が特徴です。治療のタイミングは予後を大きく左右するので、早めの対応が鍵となります。
治療開始の理想的なタイミング
- 発症から48~72時間以内: 研究や臨床経験によると、突発性難聴全般において治療が最も効果的なのは発症後できるだけ早い時期、特に最初の2~3日以内です。低音障害型の場合も同様で、このタイミングで治療を始めると聴力回復率が上がるとされています。
- 1週間以内: 発症から1週間以内に治療を開始した場合でも、一定の回復が期待できることが多いです。ただし、時間が経つほど回復率は下がる傾向があります。
- 2週間以上経過後: 発症から2週間を超えると、自然回復や治療による改善が難しくなるケースが増えます。この時点では、症状が固定化しつつある可能性が高く、完全回復は期待しづらくなります。
なぜ早いタイミングが重要か
低音障害型感音性難聴は、内耳の障害(例えば内リンパ水腫や血流障害)が原因と考えられることが多く、早期に介入することで炎症や浮腫を抑え、聴覚細胞のダメージを最小限に留められる可能性があります。特にステロイド治療が一般的に使われますが、その効果は発症からの時間に強く依存します。鍼灸治療の場合も開始時間は早ければ早いほど予後がいいという統計があります。
治療の流れとタイミングの目安
- 即時(発症当日~3日): 耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査(オージオグラム)で低音域の低下を確認。ステロイド(経口または点滴)が処方されることが多いです。
- 発症4~7日: 初期治療で効果が見られない場合、追加治療(例: 高気圧酸素療法や血管拡張剤)が検討されることもあります。
- 発症1週間以降: 経過観察を行いながら、残存症状への対処(補聴器の検討など)が焦点になる場合も。
低音障害型はメニエール病との鑑別が必要な場合があり、めまいや耳鳴りの有無も治療方針に影響します。もし症状が反复するなら、突発性難聴とは異なるアプローチが必要になることもあります。ですので、発症したらできるだけ早く専門のところに相談するのがベストです。
当院には病院の治療と並行して、早い段階から鍼灸治療を始める患者さんも数多くいらっしゃいます、短期集中する形で積極的に治療を受ける場合、回復率が確実に上がります。いつ鍼灸治療を始めるか迷う方なら、気軽に当院までお問い合わせください。
健康堂鍼灸院整骨院 久我山院
西荻窪院
併せて読みたい記事: