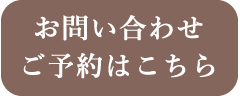突発性難聴か メニエール病か どっち?!
2025/01/13

突発性難聴とメニエール病は当院の来院数が多い疾患。どちらも内耳に関係する疾患であり、主に聴覚や平衡感覚に影響を及ぼします。症状や病態など結構似てるところがあり、プロの先生でも鑑別しにくいときがあります。今日鑑別のポイントを纏めました。
1. 発症の特徴
- 突発性難聴
- 突然発症する片側性の高度な感音性難聴が主症状。
- 発症までの前兆がないことが多い。
- 症状は通常、数時間から数日以内に進行します。
- 原因は不明だが、ウイルス感染や血流障害が関連していると考えられています。
- メニエール病
- 発作性の回転性めまい、低音域を中心とした感音性難聴、耳鳴り、耳閉感が特徴的。
- めまい発作は数十分から数時間持続し、再発を繰り返します。
- 発症には内リンパ水腫が関与していると考えられています。
2. 聴覚症状
- 突発性難聴
- 突然の聴力低下が主症状で、耳鳴りや耳閉感を伴うことが多い。
- 聴力低下は持続的であり、自然回復するケースもあるが、回復しないこともあります。
- メニエール病
- 初期は低音域の聴力低下が特徴で、発作を繰り返すごとに聴力がさらに悪化し、高音域にも影響が出る場合があります。
- 難聴は発作中に悪化し、発作後には一部回復するのが典型的です。
3. めまい
- 突発性難聴
- めまいを伴うこともありますが、持続性や回転性のめまいは稀。
- 平衡感覚障害があっても一時的で軽度です。
- メニエール病
- 発作性の激しい回転性めまいが特徴で、日常生活に支障をきたすことが多い。
- 発作中は嘔気や嘔吐を伴うこともあります。
4. 診断方法
- 突発性難聴
- 突然の片側性難聴が診断基準の中心。
- 聴力検査で感音性難聴を確認。MRIで聴神経腫瘍や脳血管障害を除外することが重要。
- メニエール病
- 反復する回転性めまいと、聴覚症状の組み合わせが診断の要。
- 聴力検査で低音域優位の感音性難聴を確認。
- 電気生理学的検査や内耳MRIで他疾患を除外することも行われます。
5. 治療の違い
- 突発性難聴
- 早期治療が重要で、発症後2週間以内に治療を開始することが推奨されます。
- ステロイド療法や高気圧酸素療法が有効とされています。
- 初期症状なら鍼灸治療が有効とされています
- メニエール病
- 根治療法はないが、内リンパ水腫の軽減を目指した治療が行われます。
- 食事療法(減塩)や利尿薬の投与、場合によっては手術も検討されます。
- めまい発作には抗めまい薬や制吐薬を使用します。
- 種類によりますが、鍼灸治療は有効な報告が多いです
鑑別の要点
- 突発性難聴は「突然の難聴」が主症状であり、めまいが軽度または無い場合が多い。
- メニエール病は「再発性の回転性めまい」と「難聴や耳鳴り」が特徴的であり、めまいの有無が鑑別の重要なポイントとなります。
適切な診断と治療を行うためには、詳細な問診や聴力検査、場合によっては専門的な画像検査が必要です。
突発性難聴もメニエール病も鍼灸治療により改善されることが多いです、気軽に健康堂鍼灸院整骨院までお問い合わせください。
健康堂 久我山院
西荻窪院
併せて読みたい記事:
● 突発性難聴か メニエール病か どっち?!