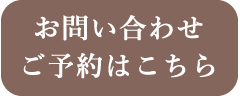Medical content 診療内容 突発性難聴・耳鳴りと効果的な鍼灸治療
突発性難聴と耳鳴り
-
突発性難聴とは

突発性難聴は、予兆なく耳の聞こえが悪くなる病気です。朝起きたら耳がよく聞こえなかった、電話の音が聞こえなくなったなど、突然症状が表れることがほとんどですが、数日かけて悪化することもあります。原因ははっきりとはわかっていませんが、音を感知して脳に伝える役割を担っている内耳のウイルス感染や血流循環障害ではないかといわれています。そのほか、ストレスや過労、睡眠不足、糖尿病などが関係していると考えられています。
-
突発性難聴の症状
代表的な症状は、病名の通り難聴です。難聴の度合い、聞こえにくさは人によって異なります。ほとんどの音が聞こえない場合もあれば、高音など一部の音が聞こえない場合もあります。多くの場合、片方の耳にのみ症状が表れます(まれに両方のこともあります)。難聴と前後して、耳鳴りやめまい、吐き気などが起こることもあります。これらの症状は一度だけで、繰り返されることはありません。耳鳴り:低い音の聞こえが悪い場合、「ブーン」「ボー」など響く感じの音が鳴ります。高い音の聞こえが悪い場合、「キーン」などの金属音になります。低い音も高い音も聞こえが悪い場合、混じり合うのでセミが鳴く「ジー」などの音が聞こえます。
また、突発性難聴は子どもがかかることもあります。発症頻度は大人よりも少ないですが、難聴の度合いが大人に比べ高度な場合が多く、めまいなども合併しやすいので注意が必要です。 -
突発性難聴の原因
音は外耳 - 鼓膜 - 耳小骨 - 蝸牛 - 聴神経 - 脳へと伝わりますが、突発性難聴は蝸牛(かたつむり)の中の音を感じる神経細胞(有毛細胞)の障害で起こるといわれています。
・過度のストレス(過労、心労、睡眠不足)により、蝸牛(かたつむり)を流れる細い血管の血液の流れが悪くなり、神経細胞への栄養が足りなくなる。
・心臓病、動脈硬化、糖尿病、高血圧などの持病がある患者さんにおいては、小さな血のかたまり(血栓)で血管がつまってしまい、酸素が行き渡らなくなる。
などが考えられています。 -
治療
病院で行われる"標準的"な治療は、血液循環を良くすることを目的とした、ステロイドやビタミン剤などの薬物療法です。また、発症から2週間頃を境に、症状が固定化、つまり良くも悪くも変化しない状態になる傾向があるため、できる限り早く医療機関を受診し、治療を開始することが予後に影響すると言われています。ただし、これもあくまで目安で、早期治療をしても改善しないケースもあります。突発性難聴の予後として、3分の1は改善し、3分の1は多少の回復は見られるものの完治はせず、残りの3分の1はまったく回復しないとも言われています。特に初期症状が重度の方は、症状が固定化しやすく、治りにくい傾向にあります。
-
鍼灸治療
突発性難聴に対する鍼灸治療は、耳周辺、頚部の筋緊張の改善が重要です。特に頚の筋緊張の改善が椎骨動脈の血流(首の奥にある動脈)に影響し、間接的に聴力改善に関わると考えられます。また副症状として多い「耳鳴り」、「めまい」などにも鍼灸は効果的です。

-
予後
● 治りやすい方
低い音のみ聞こえが悪い
聞こえがそれほど悪くない
若い方
● 治りにくい方
聴力検査で聞こえが悪い
高血圧、糖尿病、腎臓病などの内科の病気がある
治療に来るのが2週以上と遅れた
治療を勧められたが断った
-
耳鳴りについて

耳鳴りとは、外界から音が耳に入っていないのに関わらず音を感じる症状をいいます。多くは耳の病気と一緒に起こりますが、全身的な病気によるものや、心理的な要因がきっかけで耳鳴りを生じていることもあります。
-
耳鳴りの原因
外からの音の刺激がないにもかかわらず、耳や頭の中で音を認識する状態のことを耳鳴りといいます。 また、難聴によって脳が過敏に反応するようになり、脳によって耳鳴りという音が作り出されている状態も考えられます。
耳鳴りの正体は「脳が過敏になっていることがほとんどです。耳鳴りは、耳で鳴っているのではなく、脳で鳴っているのです。 -
耳鳴りの分類
自覚的耳鳴りの原因には、全身的な疾患や薬の副作用、またはストレスや疲労で起こることもあり、以下の3つに分類されます
感音性耳鳴り
内耳、聴神経、聴覚中枢(脳幹、大脳皮質)に障害があることが原因となるものをいいます。内耳炎、メニエール病、老人性難聴、突発性難聴、騒音性難聴、聴神経腫瘍などがこれにあたります。また、ストレイプトマイシン、シンプラチンなどの抗がん剤などの薬物は内耳を冒し、耳鳴りを生じさせます。
全身的疾患が原因の耳鳴り
低血圧や高血圧など循環器系の病気や、血液・リンパ系動脈硬化、糖尿病、さらに脳神経系の疾患に伴って耳鳴りが現れるものをいいます。
ストレスが原因の耳鳴り
心身のストレスによって耳鳴りが起きたり、増殖して感じたりすることがあります。
また、生理的耳鳴りの原因は、無音状態により鼓膜が緊張することにあり、他覚的耳鳴りの原因は、耳の周囲の不調(顎関節症や顎の筋肉の腫れなど)にあります。
-
①健康堂では、開業19年以来、数多くの難聴の患者さんはご来院され、施術を通して、症状が改善されました。
耳の症状に対する治療法も当院が得意とする治療の一つです。
特に突発性難聴、低音障害型感音性難聴、加齢性難聴、騒音性難聴に対しては、鍼灸治療の効果が期待できます。
健康堂では耳症状(難聴、耳鳴、耳閉塞感、耳の響き、耳の痛み、めまい、中耳炎など)の発症した症例に対して、単独および薬物治療と併用する方法で鍼灸治療を実施し症状を軽減または改善してきました。
病院の治療では、理想的には発症48時間以内、出来れば14日以内の治療開始が望まれます。治療期間は2~3週間で、発症1か月以降の効果はあまりないようです。
健康堂の鍼灸治療ではおよそ発症3か月までは改善が見られます(それ以降に改善することもあります)。

-
②独自な治療法。
独自な鍼灸治療、トウ氏奇穴、奇経法を使い、効果の高いツボ刺激をすることにより筋肉や神経の働きが活発になり、内耳血液の循環をよくすることになり、難聴の症状改善につながります。また鍼灸で自律神経のバランスを調整して、自律神経の異常による症状にも効果を挙げられます。
当院における鍼灸治療は東洋医学の脈診、腹診を行い、治療目標は体質を改善することによる根本原因の除去です。薬物治療のような対処療法ではありません。
そのため、鍼灸治療で改善できた症状は再発しにくいのが特徴です。
薬物治療により改善が見られない場合や症状を繰り返すような場合は当院の鍼灸治療をお勧めいたします。

-
③カウンセリングと自宅ケアはしっかり指導
施術後の変化を確認頂き、お身体の状態や今後のアドバイスをさせていただきます。
来院頻度や自宅でのケア方法、気になることなどを丁寧にお答えします。

-
④マスコミも注目
開業以来、多数のマスコミに取材され、冷総院長は『プレジデント』に「つぼの達人」として紹介されました。

-
病院の治療と並行して鍼灸治療を行うことをお勧めします。症状が残らない可能性を高めるために、鍼灸治療も早期に行った方が良いです。実際に、すぐに鍼灸治療を始めた方が、症状の緩和・完治した例を多数見てきました。
また突発性難聴が治らなかった方でも、あきらめない気持ちは大切かもしれません。医療は不確実なもので絶対はないです。治療をして、すぐには症状に変化が現れなかった方でも、長期間鍼灸治療を受けることで、耳周りの血流改善を促し、全身の調子を整えれば、症状に変化が現れるかもしれません。 -
金子 育 先生

内科医師・漢方医 「木蘭堂」グループ代表
長年、内科女医として鍼灸・漢方診療に従事し、立川・国立の「木蘭堂グループ」を主宰。推薦の声:
病院や他の治療院に通っているが、良くならない、そのような方にオススメいたします!
当院では腰痛、関節痛、自律神経が乱れる方、様々な難病症状を訴える方が多数みえます。そのような方にを最大限に診療を行うのですが、完全改善は非常に難しいというのが現状です。
そのような時に、いわゆる代替医療である鍼灸・手技療法は非常に有効で、医療補助的な役割というよりは、むしろメインの施術になると考えています。「手当て」である鍼灸や手技療法は、その手を通じて心や気を伝達する作用も相まって、医学の限界をものともせずに症状を改善させる不思議な効果があります。
健康堂鍼灸院整骨院の施術は、その心や気を大切にする、暖かく、かつ熱いものを感じさせてくれます。心のある施術とそうではない施術、どちらが効果的かは明らかであると思います。
冷総院長の元で、厳しいトレーニングを受けたスタッフたちは、一様にその心を手のひらから伝えてくれるでしょう。
当院からも多くの方を紹介し施術していただいております。非常に信頼のおける存在です。 -
菅 民生 先生

中国医師、中国推拿(中国式マッサージ)の第一者
推薦の声:
冷総院長とご縁があり、私の弟子として十数年付き合ってます。修業される時期、彼は患者さんへ強い熱意、真摯に学び、働く姿を見て何度も感銘を受けました。 院全体に関しても、冷総院長をはじめ、スタッフの皆さんも患者様の様々な悩みを見極め解決してくださるので、腰痛や、深い悩み、難病をお持ちの方など、どなたでも安心して通えて笑顔で帰ることができると思います。 私は、自信を持って冷総院長、健康堂鍼灸院整骨院を推薦させていただきます。 -
伊藤 賢一 先生

人形町いとう鍼灸院 院長
推薦の声:
健康堂鍼灸院整骨院を推薦します 健康堂鍼灸院整骨院は、15年以上に渡り、地域の患者様から強い支持を受けている、冷鉄軍(れいてつぐん)総院長が率いる治療院グループです。 スタッフ教育に定評があり、高いレベルの技術を各スタッフが習得しています。
外傷治療、慢性疼痛、自律神経失調症などの多岐に渡る適応範囲を持ち、さらにリフレクソロジーやアロママッサージなどの施術までもカバーしています。 ここを卒業したスタッフは、日本全国に散らばり、自院を開業したり高級ホテルなどで活躍しています。
私は健康堂鍼灸院整骨院を推薦します。 -
治療例
● 健康堂の症例NO.436: 女性 自営業 ステロイド剤治療は改善されなかったが…
当院の治療の特徴
推薦する医師などの声
● 健康堂の症例NO.440:50代女性 鍼灸で最初改善されましたが、突然めまいが現れ、悪化しました…
料金
治療料金 自由診療 6800円/回(約60分)
初診料 1000円
初回の方は是非クーポン券をご利用ください↓
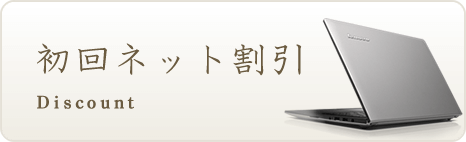
Health blog 難聴・耳鳴り / 関連記事
● 低音障害型感音難聴なら 鍼灸治療は効くのか?● 鍼灸治療の科学的な根拠は?
● 突発性難聴か メニエール病か どっち?!
● 突発性難聴と鍼灸治療