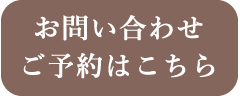Medical content 診療内容 顎関節症と効果的な矯正・鍼灸治療
顎関節症

顎関節症とは、顎の関節である「顎関節」に関する疾患で、1996年に日本顎関節学会は、
「顎関節症とは、顎関節や咀嚼筋の疼痛、関節雑音、開口障害または顎関節運動以上を主徴候とする慢性疾患の総括的診断名であり、その病態には咀嚼筋障害、関節包・靭帯障害、関節円盤障害、変形性関節症などが含まれる」
と定義しています。
顎関節症は20~30代の女性に好発しますが、最近はストレス社会の影響からか、男性でも顎関節症を訴える人が増えてきています。
顎関節症の原因
- ・顎顔面の外傷(顔面打撲や事故による外傷)
- ・全身疾患、栄養不良
- ・顎関節の形態異常
- ・精神的ストレス、うつ、不安因子
- ・心理特性、性格特性(神経質、几帳面、すべてに一生懸命に対応する)など
- ・女性の閾値の低さ
- ・パラファンクション(異常機能活動:歯ギシリ、持続的食いしばりのこと)
- ・精神社会的因子
- ・睡眠障害
- ・口腔習癖、アゴの酷使
- ・不良姿勢( 猫背)、頬杖、うつ伏せ寝
- ・不正咬合、骨格異常
- ・不良補綴物
- ・大開口や硬い食物の摂取
- ・長期的偏咀嚼
主病変が咀嚼筋障害による「筋性」と、顎関節(下顎窩、関節円板、下顎頭、関節包)障害による「関節性」の二つに大別されます。日本において顎関節症の多様な病態に対応するため、有限責任中間法人日本顎関節学会はⅠ~Ⅴ型に分類を行い、広く臨床に使用されています。
| Ⅰ型 | 咀嚼筋障害を主徴候とし、その病理は筋緊張と筋スパズム(筋肉が一部血流不全などによって硬くなった状態)、筋炎です。顎関節部の運動痛と運動障害を少し感じることがあり、筋痛がとても強い事が特徴です。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ型 | 関節包、関節靭帯、円板後部組織の慢性外傷性病変を主徴候とし顎関節部の運動痛と圧痛が強く、関節雑音があります。 筋痛は弱く、関節鏡下で病変がわかります。 |
||||
| Ⅲ型 |
関節円板の転位や変性、穿孔、線維化を主徴候とし、クリッキングと呼ばれる関節雑音が顕著であり、筋痛はなく顎関節部の疼痛は弱い事が特徴です。
|
||||
| Ⅳ型 | 変形性関節症。関節軟骨の破壊、下顎窩や下顎頭の骨吸収や変性・添加、関節円板や滑膜の変性異常などの退行性病変を主徴候とし、クレピタス音(ジャリ、ザリッなど)と呼ばれる関節雑音が顕著で、レントゲン診断上も大きな異常を認めるようになります。 | ||||
| Ⅴ型 | 上記のⅠ~Ⅳ型のいずれにも該当しませんが、顎関節領域に異常症状を訴える心身医学的な要素を含むもがあります。 |
顎関節症の症状
- 筋肉の痛み、こり:顎の周辺、こめかみ、首すじの痛み、肩こり。
- 関節の痛み:顎関節部や耳の穴の内前方あたりの痛み。
- 顎の動きの制限:顎を動かしにくい、大きく開けられない、物がよく噛めない、どこで噛めばいいのかわからない。
- 関節の異常音:顎を動かした時にカクンあるいはギシギシ、ミシミシ音が聞こえる。
- その他の症状:上記の症状に伴って、さらに頭痛、耳鳴り、手足のしびれ、めまい、鼻やのどの違和感。
-
健康堂では、開業16年以来、数多くの顎関節症の患者さんはご来院され、施術を通して、症状が改善されました。
顎関節症に対する治療法も当院が得意とする治療の一つです

-
独自な治療法。
当院の顎関節症の治療目的は、顎関節症患者にできるかぎりの回復の機会を提供することと顎関節症の完全な回復までの時間を短縮することです。
顎関節症に対して、当院は細めの鍼と電気の併用でより良い成果を上げています。治療は顎関節症の頑固さに応じて、多岐に渡って行います。当院は弁証論治の基本を元に、特殊な電気針治療法、関節矯正を組み合わせることで、最大限の効果を引き出します。そして顎関節症の回復で、顎関節症患者さんの生活の質を向上させるのに役に立っています。
当院における鍼灸治療は東洋医学の脈診、腹診を行い、治療目標は体質を改善することによる根本原因の除去です。薬物治療のような対処療法ではありません。
そのため、鍼灸治療で改善できた症状は再発しにくいのが特徴です。
薬物治療により改善が見られない場合や症状を繰り返すような場合は当院の鍼灸治療をお勧めいたします。

-
カウンセリングと自宅ケアはしっかり指導
施術後の変化を確認頂き、お身体の状態や今後のアドバイスをさせていただきます。
来院頻度や自宅でのケア方法、気になることなどを丁寧にお答えします。

-
マスコミも注目
開業以来、多数のマスコミに取材され、冷総院長は『プレジデント』に「つぼの達人」として紹介されました。

-
金子 育 先生

内科医師・漢方医 「木蘭堂」グループ代表
長年、内科女医として鍼灸・漢方診療に従事し、立川・国立の「木蘭堂グループ」を主宰。推薦の声:
病院や他の治療院に通っているが、良くならない、そのような方にオススメいたします!
当院では腰痛、関節痛、自律神経が乱れる方、様々な難病症状を訴える方が多数みえます。そのような方にを最大限に診療を行うのですが、完全改善は非常に難しいというのが現状です。
そのような時に、いわゆる代替医療である鍼灸・手技療法は非常に有効で、医療補助的な役割というよりは、むしろメインの施術になると考えています。「手当て」である鍼灸や手技療法は、その手を通じて心や気を伝達する作用も相まって、医学の限界をものともせずに症状を改善させる不思議な効果があります。
健康堂鍼灸院整骨院の施術は、その心や気を大切にする、暖かく、かつ熱いものを感じさせてくれます。心のある施術とそうではない施術、どちらが効果的かは明らかであると思います。
冷総院長の元で、厳しいトレーニングを受けたスタッフたちは、一様にその心を手のひらから伝えてくれるでしょう。
当院からも多くの方を紹介し施術していただいております。非常に信頼のおける存在です。 -
菅 民生 先生

中国医師、中国推拿(中国式マッサージ)の第一者
推薦の声:
冷総院長とご縁があり、私の弟子として十数年付き合ってます。修業される時期、彼は患者さんへ強い熱意、真摯に学び、働く姿を見て何度も感銘を受けました。 院全体に関しても、冷総院長をはじめ、スタッフの皆さんも患者様の様々な悩みを見極め解決してくださるので、腰痛や、深い悩み、難病をお持ちの方など、どなたでも安心して通えて笑顔で帰ることができると思います。 私は、自信を持って冷総院長、健康堂鍼灸院整骨院を推薦させていただきます。 -
伊藤 賢一 先生

人形町いとう鍼灸院 院長
推薦の声:
健康堂鍼灸院整骨院を推薦します 健康堂鍼灸院整骨院は、15年以上に渡り、地域の患者様から強い支持を受けている、冷鉄軍(れいてつぐん)総院長が率いる治療院グループです。 スタッフ教育に定評があり、高いレベルの技術を各スタッフが習得しています。
外傷治療、慢性疼痛、自律神経失調症などの多岐に渡る適応範囲を持ち、さらにリフレクソロジーやアロママッサージなどの施術までもカバーしています。 ここを卒業したスタッフは、日本全国に散らばり、自院を開業したり高級ホテルなどで活躍しています。
私は健康堂鍼灸院整骨院を推薦します。料金
治療料金 保険併用診療 5200円/回(約55分)
自由診療 6800円/回(約60分)
初診料 1000円
初回の方は是非クーポン券をご利用ください↓
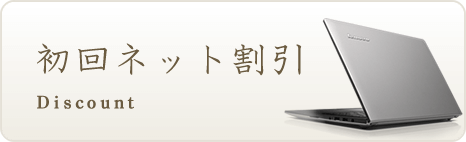
顎関節症の予防
- 物を食べる時に片方の顎だけで噛む。
→ 両方の歯で噛むようにする。 - 横を向きながらテレビを見るなどして、顔をまっすぐ向けずに食事をする。
→ まっすぐ向いて食べる。 - 長時間のほほ杖、または頻度の多いほほ杖。
→ ほほ杖をつかない。 - 顎と肩で電話をはさむ。
→ 電話は手で持つかフリーハンドのツールを使う。 - 食いしばり。(日中)
→ 常に顎の力が抜けているかチェックをする。(口を大きく開ける癖を付けるとよい) - 歯ぎしり。(夜間)
→ これは意識的に気を付けようがないので、とりあえずマウスピースなどを付ける。
根本的な対策は、脳や体の緊張を取ることが必要。整体などを受けるのも良い。 - 姿勢の悪さ。
→ 常に姿勢を意識すること。また、体操などをして、体が固まらないように心がける。
- 物を食べる時に片方の顎だけで噛む。